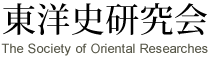東洋史研究会大会
2025年度 東洋史研究会大会
日 程:2025年11月1日(土)
時 間:午前10時~午後5時
会 場:京都大学文学研究科 第3講義室 ※オンラインも併用します。
| 午前の部 | 午前10時~12時 |
|---|---|
| 葉 勝 | 「康煕中期盛京における八旗の食糧問題と地方情勢」 |
| 板橋 暁子 | 「四夷と偏覇のはざま」 |
| 太田 麻衣子 | 「劉邦故里からみた南と北の結節点」 |
| 午後の部(1) | 午後1時~2時45分 |
| 早矢仕 悠太 | 「12世紀以降ハナフィー派法学書における公共物利用学説の系譜」 |
橋爪 烈 |
「スンナ派カリフの誕生――アッバース朝カリフ政権の支配の正当性とその変遷―― 」 |
| 嘉藤 慎作 | 「ムガル朝の勅令とオランダ東インド会社の特権」 |
| 午後の部(2) | 午後3時15分~5時 |
| 小野 泰教 | 「厳復『天演論』の中国思想史上の位置」 |
| 廣瀬 憲雄 | 「百済王都漢城陥落前後の北魏―高句麗関係」 |
| 石川 禎浩 | 「情報より見たる「長征」に関する二、三のこと」 |
参加方法
① 大会への参加にはWeb上での事前登録が必要です。会場で参加される方も同様です。
どなたでも参加できます。
なお、会場で参加される方は、会場参加費1,000円(資料代を含む)をいただきます。
登録申請フォームには下記のアドレスまたはQRコードからお入りください。
締め切りは10月29日(水)です。
※今年は2年に1度の評議員改選の年に当たっておりますので、会員の方は登録申請を行った後、下のフォームから投票も行ってください。
https://forms.gle/bZKNdDo4VGSzgsay7
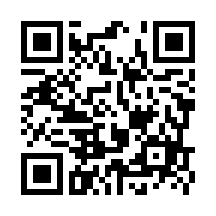
② 発表者のレジュメは、対面参加者には紙媒体で配布、オンライン参加者には当日のみ公開する「専用サイト」からアクセスしていただきます。「専用サイト」のアドレスは、申請フォームの入力後、自動送信されるメール内で通知致します。
③ 大会終了後、懇親会を開催致します(会費4,000円)。 多数ご参加ください。
- ※今年は2年に1度の評議員改選の年に当たっています。大会への参加不参加にかかわらず、会員の方は、下記のアドレスまたはQRコードから入り、5名連記での投票をお願いします。
https://forms.gle/JvH7NVSVufUJerA58
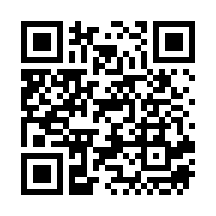
発表要旨
康煕中期の盛京における八旗の食糧問題と地方情勢
葉 勝
盛京地区(盛京将軍轄区)は清の入関以降、満洲地域の核心区、八旗軍の本拠地、人員・物資の集散地として、主に満洲地域の人員を調達して関内の八旗兵を補充する役割を担っていた。しかし康熙20年(1681)、清朝が三藩の乱を平定し、関内の軍事的緊張が解けると、清朝は満洲地域の軍事力強化に転じ、アムール川流域におけるロシア帝国との国境紛争の解決を図ったのである。更に康熙帝は翌年に満洲地域を東巡し、軍事視察と配置を行った。
こうしたなかで、対ロシア後方基地であった盛京地区では、八旗の軍事力を徐々に強め、康熙28年(1689)のネルチンスク条約締結後も強化を続けた。康熙29年(1690)、康熙35年(1696)における対ジュンガル戦争でも、盛京八旗は満洲地域の核心部隊として、後方支援と側翼からの牽制の任務を果たし、東方戦線の人馬、物資の供給を請け負ったのである。
その一方で、盛京地区では、康熙21-37年(1682-1698)に自然災害が頻発し、農業生産が不安定であったという記録が多く残っている。康熙32-36年には、5年連続で甚大な自然災害が発生し、旗田・皇荘・民田の不作、糧価の高騰、住民の逃亡があったという。ようやく収穫量が増えたのは、康煕38年(1699)のことである。また、清朝は康熙7年(1668)に「遼東招民授官例」を廃止しており、漢人移民の満洲地域への移動を奨励しなかったため、これ以降農業生産人口、起科民田の面積、賦税額はあまり伸びていない。
このような状況下において、盛京八旗はこの間に如何にして拡大する軍需、特に糧食の供給を保障し、戦力を保持したのであろうか。本発表はこの問題に焦点をあて、康熙朝『黒図档』に見られる満文档案資料を主史料にして、実録、地方志、八旗志等の官書や時人の著述を参照し、この問題及び当時の盛京地区における情勢の解明を試みるものである。
四夷と偏覇のはざま
板橋 曉子
五胡十六國時代の「十六國」は崔鴻『十六國春秋』に由來するが、一方で、當該時代の諸政權に對する後世の認識に大きな影響を與えてきたのは唐修『晉書』載記であり、同じ唐代に成立した他の史書とも一定の相關關係が見られる。
最終卷(序傳)を除く李延壽『北史』列傳の末尾には、卷九三に僭僞附庸傳、卷九四~九六に四夷傳、卷九七に西域傳、卷九八に蠕蠕などの傳、卷九九に突厥などの傳が立てられている。このうち僭僞附庸傳の序において李延壽
は、先行する史書では劉淵・石勒らの五胡諸政權が「四夷」に編入されていることを非とし、唐太宗が唐修『晉書』に載記を設けたことを肯定的に記す。李延壽はまた、僭僞附庸傳を北魏道武帝期以降に興亡した勢力の記錄と位置づけ、赫連氏の夏など五胡十六國時代後期の華北非漢人政權(および後梁)を立傳している。一方で、卷九六には氐、卷九八には鮮卑段部など、五胡十六國時代を含む時期の華北に割據した非漢人勢力の一部を僭僞附庸傳とは別に立傳しており、この點も唐修『晉書』と同樣の分類が見られる。
本報告では、唐修『晉書』載記の枠組に先立って成立した崔鴻『十六國春秋』佚文を多く傳える『太平御覽』偏覇部、五胡諸政權の一部を扱う『通典』邊防、氐や稽胡など華北内部の勢力も立傳される『周書』異域傳、そのほか史書・類書・石刻史料等を檢討し、後世の文獻において五胡十六國~北朝期の華北非漢人政權が如何に分類されたか、とりわけ「四夷」とそれ以外とに如何に切り分けられたのか、その背景を考察する。
劉邦故里からみた南と北の結節点
太田 麻衣子
漢王朝を樹立した劉邦は沛県豊邑の人である。沛は戦国後期に宋が滅亡したのち楚の支配下に入ったとされる一
方、豊については秦が魏を滅ぼす際に魏の都が遷された地だという説も伝わっている。また、馬王堆漢墓帛書「戦国縦横家書」には秦の侵攻に備えて魏王は単父に遷るべきだという弁論が記されているが、豊は沛と単父の中間に位置する邑だった。本発表ではこうした劉邦故里の歴史地理について水路をふまえながら考察する。
沛を流れる泗水は淮水の支流だが、史念海氏は春秋後期に呉が長江と淮水を邗溝により結び、黄河の支流である済水を菏水により泗水と繋いだ結果、済水・菏水の合流地点にある定陶が「天下之中」として経済的繁栄を極めたことを指摘する。すなわち泗水は戦国時代にはすでに黄河と長江を結ぶ「大運河」の一部になっていたのであり、前三一二年に越が魏に送った船団も泗水を経由したものと考えられる。秦代に劉邦が亭長を務めていた泗水亭(泗上亭)
は、そうした南北に行きかう人や物の通過地点に位置していたのである。
沛や豊、単父、定陶はいずれも戦国時代には宋に属しており、前二八六年に斉が宋を滅ぼしたのちは楚や魏だけでなく秦もまた宋の故地を獲得した。劉邦により戦国時代の枠組みを脱した統一王朝が樹立された背景として、諸地域に通じ、諸勢力が交錯していた劉邦故里の歴史地理的環境は、看過できないと考えられる。
12世紀以降ハナフィー派法学書における公共物利用学説の系譜
早矢仕 悠太
本報告では、イスラーム法学における牧草地や水源といった所有者が特定されていない物、いわゆる公共物に対する利用をめぐる学説の変遷を追う。公共物利用に関する法学説については、伝統的な法学書において一定の紙幅が割かれながらも、規定の現実性への疑義やイスラーム世界における国事と法学の消極的関係から、歴史研究の俎上にあげられてこなかった。一方で、同時代とそれ以降の法学者の間で受け入れられた法学書の記述は、イスラーム法体系を支える思考を確かに投影している。なかでも、公共物利用学説の一部は「所有権」の原始取得をめぐる議論も含んでおり、その理解はイスラーム法学における所有とその権利化のプロセスを描くために不可欠である。
本報告は関連する学説の変遷を追うために、古典法学が完成する12世紀から、西洋近代法学との邂逅によってイスラーム法の在り方に変容が迫られた19世紀にいたるまでを対象に、スンナ派法学の一つであるハナフィー派法学、その法学者の間で権威として参照されてきた法学書収録の学説を素材として、法学書間の引用関係とともに、権威的な学説への加除を分析の主眼におく。学説の系譜を分析することで示唆されるのは、ハナフィー派法学における所有をめぐる観念の変容が、イスラーム法体系の変容と象徴される1877年施行のオスマン民法典メジェッレ以前に遡るということである。
スンナ派カリフの誕生
―アッバース朝カリフ政権の支配の正当性とその変遷―
橋爪 烈
749年から1258年までおよそ500年にわたって続いたアッバース朝カリフ政権は、支配の正当性を主張するにあたって、その根拠と主張の対象を変えてきた。王朝成立前後は預言者の一族に連なる家系であることやアリーの権威の受け継いだことを掲げ、ウマイヤ朝打倒を成し遂げる。その後、シーア派諸勢力との対抗上、預言者の叔父アッバースの権威の継承者であることを強調し、また預言者の知的後継者と自認する伝承主義者に対してカリフ権の至上性を確立すべく神のカリフたることを主張する。7代カリフ・マアムーンに始まるこの試みが瓦解すると、アッバース朝カリフの権力そのものに陰りが見え始め、10世紀初頭に政治の実権をほぼ喪失する。
一般的には、この後アッバース朝カリフは軍事政権に支配の正当性を付与する役目を負うのみの存在として、政治史研究の主たる対象から外れることになる。そして1258年のモンゴルによる王朝滅亡を迎えるが、この2世紀強の期間、アッバース朝カリフたちが何ら主体的な行動を起こさなかったわけではない。
本報告はこの2世紀の間に、アッバース朝カリフによって主導されたカリフ権力再興の活動とその帰結について考察を行う。題目に示したように、アッバース朝カリフは最終的に「スンナ派カリフ」となることで、自らの支配の正当性を主張し、併せて失われた権力回復の拠り所にしようとした。その試みはモンゴルの到来によって不首尾に終わるが、この試みこそが、カリフのスンナ派化と現在まで続くカリフ制再興の動きの起点となった可能性を指摘する。
ムガル朝の勅令とオランダ東インド会社の特権
嘉藤 慎作
オランダ東インド会社がムガル朝において享受した特権とは一体いかなるものであったのか。インド亜大陸西北岸の港市スーラトに所在した同会社の商館で1740年から49年にかけて商館長を務めたヤン・シュレーデルは自身の覚書の中でこれについて見解を記している。
シュレーデルによれば、特権とは、本来、同等の権利・義務を有するべき他者に対して、自らのみを有利な立場におく、あるいは特定の義務を免除された状況を与える権利を指した。この考えに基づくオランダ東インド会社のムガル朝における特権とは、外来者としてムガル朝の在来住民と同等の権利を享受しながら、同王朝の法の適用をいくつかの点で免れるという状態を会社に対して保障する諸権利を意味した。こうした諸権利は、会社にとって上位権力であるムガル皇帝の発出した勅令によって保障されるものであった。勅令は、そこで規定された権利をオランダ東インド会社に享受させるように役人らに命令をするという形で機能した。ムガル朝によって発出されたオランダ東インド会社に関する勅令・命令書のうち、同会社は計29通を自身の交易活動上の権利を保障するものと捉えていた。なかでも、1618年と1662年にそれぞれ発出された勅令・命令書2通が重要であった。前者は、上記の会社の特権を本質的に構成する10項目の権利を保障したものであり、後者は、そのほか会社にとって交易活動上必要な諸権利をまとめて保障するものであった。
厳復『天演論』の中国思想史上の位置
小野 泰教
厳復(1854-1921)がハクスリー(Thomas Henry Huxley 1825-1895)の論文を翻訳し評語を付した『天演
論』(1898)は、従来、清末における対外的危機意識の高まりを背景とする社会進化論受容の文脈で考察されることが多かった。これに対し本報告は、『天演論』を、中国思想史において盛んに議論されてきた性説の展開のうえに位置づけるものである。
『天演論』の重要な論点の一つは、人の本性の在り方についてであり、厳復は、ハクスリーが説く宇宙過程と倫理過程との関係や彼が引用するギリシア哲学、特にストア派の思想を、中国旧来の性説の概念によって訳出している。本報告では、厳復が西洋思想を訳出する際に用いた性説の概念とその用法に着目し、厳復がそもそも中国の性説をどのように理解していたのかを考察する。さらに、厳復が参照した性説にかかわる中国の文献を抽出し、それらの文献の歴代の注釈との比較により厳復の用法の特徴を明らかにする。『天演論』に見える性説の概念は、主に諸子百家の文献に基づくが、これらの文献やその注釈は、清朝考証学の成果によって、より完備され詳細になったものが少なくない。
以上のように『天演論』は、翻訳書でありながらも、清末における性説の展開を考えるうえでの重要なテキストとして、中国思想史上に位置づけることが可能であると考える。
百済王都漢城陥落前後の北魏―高句麗関係
廣瀬 憲雄
四七五年、高句麗の攻撃により百済王都漢城が陥落した事件は、朝鮮半島情勢を一変させただけではなく、三年後の四七八年に倭王武が劉宋に上表文を提出したことからも知られる通り、日本列島にも影響を与えた重要な出来事である。そのため、この事件に関しては、朝鮮史よりもむしろ日本史から多くの研究がなされてきた。
その一方、漢城陥落に先立つ四七二年に、百済は初めて北魏に遣使して高句麗討伐を求めたが、これは日本史の視点では漢城陥落の前史と位置付けられてきた。しかし、『魏書』百済伝によれば、北魏は四七五年まで高句麗と百済に複数回使者派遣を試みているので、百済による北魏への使者派遣は、北魏―高句麗関係に大きな影響を与えたと想定できる。
また同時期の北魏―高句麗間では、北魏が高句麗王女を献文帝の後宮に納れるよう求めた、いわゆる「王女入宮事件」も発生している。この事件は、四七六年に献文帝が死去することで消滅したのだが、高句麗は一度は婚姻を承諾しながら北燕が滅亡した先例を踏まえて態度を変えているので、この事件が両国関係の画期の一つであることは明らかであろう。
以上から本報告では、百済遣使事件・王女入宮事件を中心に、百済王都漢城陥落前後の北魏―高句麗関係を再検討して、高句麗による漢城攻撃の背景を探りたい。
情報より見たる「長征」に関する二、三のこと
石川 禎浩
これまで数えきれないほど論じられてきた中国共産党の「長征」(1934-36)を、「情報」という角度から分析
し、「人類史上まれにみる偉業」と称されるこの挙が如何に成し遂げられたのかを探る。またそれと並行して、この「前所未聞的故事」をとりまく虚々実々の「情報」が如何に形成され、後世の者にどれだけの影響を与えたかを検討する。本報告の「情報」は多元多層的な意味を持つ。すなわち党と軍の大移動がどのように報じられたかという外界の情報、共産党の各組織・部隊はどのように連絡をとりあったのかという内部の情報、そして共産党の首脳たちはどのような情報に基づいて行軍ルートを策定したのかという問いに集約されるような、いわば内外を相互に行き交う情報である。
最大時で8万を超える老若男女の集団が1年余りの歳月を費やして大陸を大移動する、それも数多の天険を超え、国民党軍の執拗な追撃を受けながら。長征は大きくいって三つのルートに分かれるが、事前に予定をした計画的統一行動として行われたものではない。その三集団がともに長途跋渉をなし得たのは、徴糧(食糧徴発)と買い上げに独特の技術を持っていたからではあるが、他方でモスクワのコミンテルンをはじめとする外界と直接に通信する手段を失いながらも、対国民党軍に特化した情報管理システムを有していたという事由も見逃すことはできない。いわば、長征中の中共部隊は、地主の財産没収や身代金目的の誘拐を平気で行う旧来の土匪的心性とそれを正当化する近代的理論、それに加えて、その情報を集団内で共有するための先進ツールをあわせ持った怪物として立ち現れたのである。