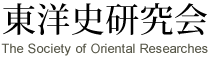『東洋史研究』既刊目録
第59~62巻
| 論説 | |
|---|---|
| 毛利 英介 | 一〇七四から七六年におけるキタイ(遼)・宋閒の地界交渉發生の原因について―特にキタイ側の視點から― |
| 阿部 幸信 | 嘉禾吏民田家莂「丘」再攷 |
| 森部 豐 | 唐末五代の代北におけるソグド系突厥と沙陀 |
| クリスチャン・ダニエルス | 雍正7年清朝によるシプソンパンナー王國の直轄地化について―タイ系民族王國を搖るがす山地民に關する一考察― |
| Mori Masao, translated by Martin Heijdra | Town Gazetteers and Local Society in the Jiangnan Region during Qing Period |
| 書評 | |
| 葭森 健介 | 安田二郎著『六朝政治史の研究』 |
| 大内 文雄 | 藤善眞澄著『道宣傳の研究』 |
| 紹介 | |
| 江村 治樹 | 黄錫全著『先秦貨幣通論』 |
| 小野 和子 | Dorothy Ko著 Every Step a Lotus; Shoes for Bound Feet |
| 論説 | |
|---|---|
| 早川 敦 | 清末の學堂奬勵について ─近代學制導入期における科學と學堂のあいだ─ |
| 高木 智見 | 古代中國の儀禮における三の象徴性 |
| 柳澤 明 | 一七六三年の「キャフタ條約追加條項」をめぐる清とロシアの交渉について |
| 蒲 豊彦 | 宣教師、中國人信者と清末華南郷村社會 |
| 書評 | |
| 江村 治樹 | 松井嘉徳著『周代國制の研究』 |
| 村上 衞 | Eiichi Motono著 Conflict and Cooperation in Sino-British Business, 1860-1911: The Impact of the Pro-British Commercial Network in Shanghai |
| 紹介 | |
| 愛宕 あもり | ヒラール・サービー著 谷口淳一・清水和裕監譯『カリフ宮廷のしきたり』 |
| 森 時彦 | 安志輝主編 新方志『新河縣志』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 宮原 佳昭 | 清末湖南省長沙における民立學堂設立と新教育界の形成について ─胡元倓と明徳學堂を中心に─ |
| 吉本 道雅 | 墨子兵技巧諸篇小考 |
| 山田 賢 | 記憶される「地域」 ─丁治棠『仕隱齋渉筆』の世界─ |
| 高嶋 航 | 天足會と不纏足會 |
| 貴志 俊彦 | 國民政府による電化教育政策と抗日ナショナリズム ─「民衆教育」から「抗戰教育」へ─ |
| 書評 | |
| 太田 幸男 | 佐原康夫著『漢代都市機構の研究』 |
| 太田 出 | 三木聰著『明清福建農村社會の研究』 |
| 紹介 | |
| 愛宕 元 | 國家文物局編『中國文物地圖集』(An Atlas of Chinese Cultural Relics) |
| 稻葉 穰 | Gordon Whitteridge著 Charles Masson of Afghanistan |
| 論説 | |
|---|---|
| 山崎 岳 | 巡撫朱紈の見た海 ─明代嘉靖年間の沿海衞所と「大倭寇」前夜の人々─ |
| 増田 知之 | 明代における法帖の刊行と蘇州文氏一族 |
| 坂出 祥伸 | 冥界の道教的神格 ─「急急如律令」をめぐって─ |
| 杉山 清彦 | ヌルハチ時代のヒヤ制 ─清初侍衞考序説─ |
| 書評 | |
| 加藤 雄三 | 中島樂章著『明代郷村の紛爭と秩序 ─徽州文書を史料として─』 |
| 紹介 | |
| 冨谷 至 | 敦煌市博物館編『敦煌文物』(Picture Album of Dunhuang Relics) |
| 高嶋 航 | Ryan Dunch著 Fuzhou Protestants and the Making of a Modern China 1887-1927 |
| 論説 | |
|---|---|
| 洪 性鳩 | 明末清初の徽州における宗族と徭役分擔公議 ─祁門縣五都桃源供氏を中心に─ |
| 岡 元司 | 南宋期の地域社會における「友」 |
| 沈 衞榮著・ 岩尾 一史譯 |
元、明代ドカムのリンツァン王族史考證 ─『明實録』チベット史料研究(一)─ |
| 上田 信 | 封禁・開採・弛禁 ─清代中期江西における山地開發─ |
| 書評 | |
| 濱田 正美 | 間野英二著『バーブル・ナーマの研究 IV 研究編 バーブルとその時代』 |
| 水越 知 | 濱島敦俊著『總管信仰 ─近世江南農村社會と民間信仰─』 |
| 紹介 | |
| 夫馬 進 | 林基中・夫馬進編『燕行録全集日本所藏編』 |
| 中砂 明徳 | Dauril Alden著 Charles R. Boxer: An Uncommon Life |
| 論説 | |
|---|---|
| 佐原 康夫 | 江陵鳳凰山漢簡再考 |
| 辻 正博 | 宋代編管制度考 |
| 櫻井 智美 | 元代の儒學提擧司 ─江浙儒學提擧を中心に─ |
| 中西 竜也 | 漢文イスラーム文獻におけるシャイフに關する敍述とその背景 |
| 新免 康・ 菅原 純 |
カシュガル・ホージャ家アーファーク統の活動の一端 ─ヤーリング・コレクション Prov.219について─ |
| 論説 | |
|---|---|
| 保科 季子 | 天子の好逑 ─漢代の儒教的皇后論─ |
| 川合 安 | 『宋書』と劉宋政治史 |
| 高井 康典行 | オルド(斡魯朶)と藩鎭 |
| 金 文京 | 明代萬暦年間の山人の活動 |
| 陳 來幸 | 廣東における商人團體の再編について ─廣州市商會を中心として─ |
| 批評・紹介 | |
| 森谷 一樹 | 江村治樹著『春秋戰國秦漢時代出土文字資料の研究』 |
| 丸橋 充拓 | 船越泰次著『唐代兩税法研究』 |
| 平田 昌司 | Benjamin A. Elman著 A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China |
| 中井 英基 | 森時彦著『中國近代綿業史の研究』 |
| 高嶋 航 | 吉澤誠一郎著『天津の近代 清末都市における政治文化と社會統合』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 中村 圭爾 | 「風聞」の世界 ─六朝における世論と體制─ |
| 横手 裕 | 劉名瑞と趙避塵 ─近代北京の内丹家について─ |
| 森川 哲雄 | 一七世紀から一八世紀初頭のモンゴル年代記について ─特に『蒙古源流』と『シラ・トゥージ』との關係を通して─ |
| 宇野 伸浩 | 『集史』の構成における「オグズ・カン説話」の意味 |
| 批評・紹介 | |
| 近藤 一成 | John W. Chaffee著 Branches of Heaven: A History of the Imperial Clan of Sung China |
| 夫馬 進 | 酒井忠夫著『増補中國善書の研究 上・下』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 水越 知 | 宋代社會と祠廟信仰の展開 ─地域核としての祠廟の出現─ |
| 箱田 惠子 | 清末領事派遣論 ─一八六〇、一八七〇年代を中心に─ |
| 間嶋 潤一 | 鄭玄『尚書注』と『尚書大傳』 ─周公居攝の解釋をめぐって─ |
| 小林 聰 | 漢六朝時代における禮制と官制の關係に關する一考察 ─禮制秩序の中における三公の位置づけを中心に─ |
| 批評・紹介 | |
| 池田 温 | 劉俊文著『唐代法制研究』 |
| 寺田 浩明 | 高橋芳郎著『宋-清身分法の研究』 |
| 奧山 憲夫 | 川越泰博著『明代中國の軍制と政治』 |
| 岡本 隆司 | 新村容子著『アヘン貿易論爭 ─イギリスと中國─』 |
| 附録 | 間野英二博士著作目録 |
| 論説 | |
|---|---|
| 井黒 忍 | 金代提刑司考 ─章宗朝官制改革の一側面─ |
| 渡邊 信一郎 | 戸調制の成立 ─賦斂から戸調へ─ |
| 市來 津由彦 | 朱熹晩年の朱門における正統意識の萌芽 ─呂祖儉と朱熹・朱門の講學を事例として─ |
| 承志(Kicengge) | 清朝治下のオロンチョン・ニル編成とブトハ社會の側面 |
| 批評・紹介 | |
| 吉川 忠夫 | 西脇常記著『唐代の思想と文化』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 山口 正晃 | 都督制の成立 |
| 岩本 篤志 | 北齊徐之才『藥對』考 |
| 本野 英一 | 辛亥革命期上海の中英債權債務處理紛爭 ─一九一〇年「ゴム株式恐慌」後の民事訴訟例分析─ |
| 志茂 碩敏 | ガザン・カンが詳述するモンゴル帝國遊牧部族連合 ─モンゴル帝國各ウルスの中核部族─ |
| 批評・紹介 | |
| 吉澤 誠一郎 | 小濱正子著『近代上海の公共性と國家』 |
| 久保 亨 | 籠谷直人著『アジア國際通商秩序と近代日本』 |
| 大谷 敏夫 | 楊啓樵著『掲開雍正皇帝隱秘的面紗』 |
| 飯島 明子 | 石井米雄著『タイ近世史研究序説』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 森谷 一樹 | 戦國秦の相邦について |
| 渡邊 孝 | 唐後半期の藩鎭辟召制についての再檢討 ─淮南・浙西藩鎭における幕職官の人的構成などを手がかりに─ |
| 新宮 學 | 明初の燕王府をめぐる諸問題 |
| 大澤 顯浩 | 姜詩 ─出妻の物語とその變容─ |
| 中 純夫 | 恆齋李匡臣緒論 ─初期江華學派における陽明學受容─ |
| 近藤 信彰 | マヌーチェフル・ハーンの資産とワクフ |
| 批評・紹介 | |
| 白須 淨眞 | 氣賀澤保規著『府兵制の研究』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 藤井 律之 | 特進の起源と變遷 ─列侯から光祿大夫へ─ |
| 工藤 元男 | 包山楚簡「ト筮祭祷簡」の構造とシステム |
| 熊谷 滋三 | 前漢の典客・大行令・大鴻臚 |
| 石井 仁 | 虎賁班劍考 ─漢六朝の恩賜・殊禮と故事─ |
| 平田 茂樹 | 宋代政治史料解析法 ─「時政記」と「日記」を手掛かりとして─ |
| 批評・紹介 | |
| 柴田 昇 | 板野長八著『中國古代社會思想史の研究』 |
| 則松 彰文 | 岸本美緒著『明清交替と江南社會 ─17世紀中國の秩序問題』─ |
| 附録 | 礪波護博士著作目録 |
| 論説 | |
|---|---|
| 楠木 賢道 | 天聰5年大凌河攻城戦からみたアイシン國政權の構造 |
| 石濱 裕美子 | ガルダン・ハルハ・清朝・チベットが共通に名分としていた「佛教政治」思想 |
| 西川 眞子 | 民國初期家庭像をめぐる知識青年の言説 ─『新青年』『申報』を中心に─ |
| 菊池 忠純 | マムルーク朝時代一五世紀末の一史書の成立過程について ─'Abd al-Basit al-Hanafiのイスラム歴八四八年/西暦一四四四年四月二〇日から一四四五年四月八日の敍述の檢討を通じて─ |
| 岩尾 一史 | 吐蕃のルと千戸 |
| 批評・紹介 | |
| 木村 秀海 | 楊寛著『西周史』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 矢木 毅 | 高麗時代の銓選と告身 |
| 伍 躍 | 清代地方官の病死・病氣休養について ─人事管理に關する一考察─ |
| 金子 肇 | 清末民初における江蘇省の認捐制度 |
| 近藤 治 | アブル・ファズルの皇帝観について |
| 批評・紹介 | |
| 小林 英夫 | 安冨歩著「『滿洲國』の金融」 |
| 江田 憲治 | 北村稔著『第一次國共合作の研究 ─現代中國を形成した二大勢力の出現─』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 井上 充幸 | 明末の文人李日華の趣味生活 ─『味水軒日記』を中心に─ |
| 張 學鋒 | 西晉の占田・謀田・租調制の再検討 |
| 西里 喜行 | 册封進貢體制の動搖とその諸契機 ─嘉慶・道光期の中琉關係を中心に─ |
| 余部 福三 | イスラームの宣教とクターマ族の國家形成 |
| 小田 壽典 | トルコ語佛教寫本に關する年代論 ─八陽經と觀音經─ |
| 雑叢 | |
| 村尾 進 | 『球雅』の行方 ─李鼎元の『琉球譯』と清朝考證學─ |