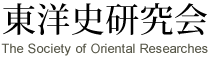『東洋史研究』既刊目録
第67~70巻
| 論説 | |
|---|---|
| 五味 知子 | 「誣姦」の意味するもの――明清時代の判牘・官箴書の記述から―― |
| 上田 裕之 | 洋銅から滇銅へ――清代辦銅制度の転換點をめぐって―― |
| 川本 正知 | バハー・ウッディーン・ナクシュバンドの生涯とチャガタイ・ハン國の終焉 |
| 中町 信孝 | マムルーク朝期の非著名知識人のライフコース――アフマド・アイニーに関する事例研究―― |
| 書評 | |
| 福島 惠 | 荒川正晴著『ユーラシアの交通・交易と唐帝國』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 青木 敦 | 南宋判語所引法の世界 |
| 大坪 慶之 | イリ問題にみる清朝中央の政策決定過程と總理衙門 |
| 澁谷 浩一 | 一七三四‐四○年の清とジューン=ガルの講和交渉について――キャフタ条約締結後の中央ユーラシアの国際関係―― |
| 二宮 文子 | 北インド農村地域におけるスーフィー教団施設――ハーンカー・カリーミーヤの事例―― |
| 書評 | |
| 毛利 英介 | 山崎覺士著『中國五代国家論』 |
| 橋本 雄 | 岡本弘道著『琉球王國海上交渉史研究』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 川本 芳昭 | 北魏内朝再論――比較史の觀點から見た―― |
| 平田 陽一郎 | 西魏・北周の二十四軍と「府兵制」 |
| 榎本 渉 | 入元日本僧椿庭海壽と元末明初の日中交流――新出僧傳の紹介を兼ねて―― |
| 貴志 俊彦 | 植民地初期の日本-臺灣間における海底電信線の買収・敷設・所有權の移轉 |
| 近藤 信彰 | 一九世紀後半のテヘランのシャリーア法廷臺帳 |
| 書評 | |
| 岡野 誠 | 辻正博著『唐宋時代刑罰制度の研究』 |
| 鶴成 久章 | 寺田隆信著『明代郷紳の研究』 |
| 唐 啓華著 望月 直人譯 |
林學忠著『從萬國公法到公法外交――晩清國際法的傳入、詮釋與應用』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 劉 欣寧 | 秦漢律における同居の連坐 |
| 鈴木 宏節 | 唐代漠南における突厥可汗國の復興と展開 |
| 小泉 順子 | 一八八○年代中葉におけるシャムの對佛・對清關係 |
| 糟谷 憲一 | 甲午改革期以後の朝鮮における權力構造について |
| 佐藤 仁史 | 清末における城鎭郷自治と自治區設定問題――江蘇蘇屬地方自治籌辧處の管轄地域を中心に―― |
| 書評 | |
| 小野寺 史郎 | 田中比呂志著『近代中國の政治統合と地域社會――立憲・地方自治・地域エリート――』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 岡村 秀典 | 古鏡研究一千年――中國考古學のパラダイム―― |
| 目黑 杏子 | 前漢武帝の封禪――政治的意義と儀禮の考察―― |
| 前島 佳孝 | 西魏宇文泰政權の官制構造について |
| 高橋 弘臣 | 南宋の皇帝祭祀と臨安 |
| 戸部 健 | 一九二〇年代後半~四〇年代天津における義務教育の進展とその背景 |
| 書評 | |
| 岡 洋樹 | 楠木賢道著『清初對モンゴル政策史の研究』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 曾布川 寬 | 三星堆祭祀坑銅神壇の圖像學的考察 |
| 坂井 隆 | ジャワ發見のベトナム産タイルの圖柄について――イスラーム文化との交流をめぐって―― |
| 榎本 泰子 | 中國音樂史から消えた流行歌――もう一つの「夜來香ラプソディー」―― |
| 書評 | |
| 李 力著 土口 史記譯 |
陶安あんど著『秦漢刑罰體系の研究』 |
| 周 東平著 山口 亮子譯 |
錢大群著『唐律疏義新注』 |
| 磯貝 眞澄 | 濱本眞実著『「聖なるロシア」のイスラーム――一七―一八世紀タタール人の正敎改宗――』 |
| 石川 禎浩 | 飯島渉・久保亨・村田雄二郎編『シリーズ 二〇世紀中國史』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 松島 隆眞 | 漢王朝の成立――爵を手がかりに―― |
| 松下 憲一 | 北魏崔浩國史事件――法制からの再檢討―― |
| 赤木 崇敏 | 十世紀敦煌の王權と轉輪聖王觀 |
| 小沼 孝博 | 一七七〇年代における清‐カザフ關係――閉じゆく清朝の西北邊疆―― |
| 書評 | |
| 森永 恭代 | 川勝守著『明清貢納制と巨大都市連鎖――長江と大運河――』 |
| 蒲 豐彦 | 菊池一隆著『中國初期協同組合史論 一九一一―一九二八――合作社の起源と初期動態――』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 渡邉 義浩 | 中國貴族制と「封建」 |
| 熊本 崇 | 宋元祐の吏額房――三省制の一檢討―― |
| 山崎 覺士 | 宋代兩浙地域における市舶司行政 |
| 竹内 房司 | ヴェトナム國民黨と雲南――滇越鐵路と越境するナショナリズム―― |
| 稻葉 穣 | 八世紀前半のカーブルと中央アジア |
| 書評 | |
| 横山 宏章・ 松井 直之 |
曾田三郎著『立憲國家中國への始動――明治憲政と近代中國――』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 佐藤 達郎 | 漢六朝期の地方的教令について |
| 山根 直生 | 程敏政の祖先史再編と明代の黄墩(篁墩)移住傳説 |
| 林 淑美 | 一九世紀臺灣の閩粤械鬪からみた「番割」と漢・番の境界 |
| 鹽野崎 信也 | 一八世紀におけるダルバンドの支配者と住民 |
| 三澤 伸生 | スレイマンⅠ世治世期の東アナトリア掌握過程――マラティヤ地方における「ティマール制」の展開―― |
| 書評 | |
| 仲山 茂 | 紙屋正和著『漢時代における郡縣制の展開』 |
| 坂井 弘紀 | 山中由里子著『アレクサンドロス變相――古代から中世イスラームへ――』 |
| 森田 吉彦 | 閻立著『清末中國の對日政策と日本語認識――朝貢と條約のはざまで』 |
| 江夏 由樹 | 荒武達朗著『近代滿洲の開發と移民――渤海を渡った人びと――』 |
| 附録 | 濱田正美博士著作目録 |
| 論説 | |
|---|---|
| 田中 一輝 | 西晉の東宮と外戚楊氏 |
| 望月 直人 | フランス對清朝サイゴン條約通告と清朝のベトナム出兵問題―― 一八七〇年代後半、ベトナムをめぐる清佛關係の再考―― |
| 城地 孝 | 丹陽布衣邵芳考――政客の活動をとおして見る明代後期の政治世界―― |
| 渡邊 美季 | 琉球侵攻と日明關係 |
| 學會展望 | |
| 向井 佑介 | 北魏の考古資料と鮮卑の漢化 |
| 書評 | |
| 中村 篤志 | 岡洋樹著『清代モンゴル盟旗制度の研究』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 太田 麻衣子 | 鄂君啓節からみた楚の東漸 |
| 張 雯 | 近代上海における坤劇と女優 |
| 金子 修一 | 唐代詔敕文中の則天武后の評價について |
| 岸本 美緒 | 清初の「文武相見儀注」について |
| 野田 仁 | 中央アジアにおける露清貿易とカザフ草原 |
| 書評 | |
| 望月 直人 | 篠永宣孝著『フランス帝國主義と中國――第一次世界大戰前の中國におけるフランスの外交・金融・商工業――』 |
| 小林 武 | 竹内弘行著『康有爲と近代大同思想の研究』 |
| 黄 東蘭 | 金子肇著『近代中國の中央と地方――民國前期の國家統合と行財政――』 |
| 深町 英夫 | 味岡徹著『中國國民黨訓政下の政治改革』 |
| 本野 英一 | 城山智子著 China during the Great Depression : Market, State, and the World Economy, 1929-1937 |
| 紹介 | |
| 磯貝 健一 | 川口琢司著『ティムール帝國支配層の研究』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 石見 清裕 | 唐代内附民族對象規定の再檢討――天聖令・開元二十五年令より―― |
| 淺見 洋二 | 校勘から生成論へ――宋代の詩文集注釋、特に蘇黄詩注における眞蹟・石刻の活用をめぐって―― |
| 黨 武彦 | 清代直隸省の治水政策──乾隆前期の子牙河治水を中心として── |
| 片桐 宏道 | ダプン考――ダライラマ政權における「武官」―― |
| 紹介 | |
| 高田 時雄 | 栄新江・李肖・孟憲実主編『新獲吐魯番出土文獻』上下二冊 |
| 論説 | |
|---|---|
| 井黑 忍 | 區田法實施に見る金・モンゴル時代農業政策の一斷面 |
| 赤坂 恒明 | ホシラの西行とバイダル裔チャガタイ家 |
| 伍 躍 | 清代における捐復制度の成立について――考課制度との相互關係を中心に―― |
| 水羽 信男 | 一九五〇年代における「民族資産階級」について──中國民主建國會の反右派鬪爭から考える── |
| 學會展望 | |
| 武内 紹人 | 古チベット文獻研究の現段階 |
| 書評 | |
| 宮本 一夫 | ロータール・フォン・ファルケンハウゼン著(吉本道雅解題・譯)『周代中國の社會考古學』 |
| 川尻 秋生 | 松本保宣著『唐王朝の宮城と御前會議――唐代聽政制度の展開――』 |
| 金 榮鎭 | 夫馬進著『燕行使と通信使』 |
| 太田 信宏 | 水島司著『前近代南インドの社會構造と社會空間』 |
| 紹介 | |
| 二階堂 善弘 | Hok-lam Chan(陳學霖)著 Legend of the Building of Old Peking |
| 論説 | |
|---|---|
| 森平 雅彦 | 高麗王家とモンゴル皇族の通婚関係に関する覚書 |
| 矢木 毅 | 近世朝鮮時代の古朝鮮認識 |
| 中 純夫 | 尹根壽と陸光祖――中朝間の朱陸問答―― |
| 桑野 榮治 | 朝鮮中宗二〇年代の對明外交交渉──『嘉靖會典』編纂の情報收集をめぐって── |
| 夫馬 進 | 一七六五年洪大容の燕行と一七六四年朝鮮通信使──両者が体験した中国・日本の「情」を中心に── |
| 書評 | |
| 山口 昭彦 | 守川知子著『シーア派聖地参詣の研究』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 杉村 伸二 | 前漢景帝期國政轉換の背景 |
| 荒川 正晴 | 遊牧國家とオアシス國家の共生關係──西突厥と麹氏高昌國のケースから── |
| 飯山 知保 | 『運使郭公復齋言行録』の編纂と或るモンゴル時代吏員出身官僚の位相 |
| 山本 明志 | モンゴル時代におけるチベット・漢地間の交通と站赤 |
| 清水 和裕 | ヤズデギルドの娘たち――シャフルバーヌー伝承の形成と初期イスラーム世界―― |
| 書評 | |
| 阿 風 | 范金民著『明清商事糾紛與商業訴訟』 |
| 論説 | |
|---|---|
| 朴 彦 | 明代における朝鮮人の遼東移住 |
| 宮 紀子 | 対馬宗家旧蔵の元刊本『事林広記』について |
| 太田 出 | 明清時代「歇家」考──訴訟との関わりを中心に── | 劉 素芬 | 一九三〇年代における日本の在華置籍船 |
| 書評 | |
| 近藤 一成 | 梅原郁著『宋代司法制度研究』 |